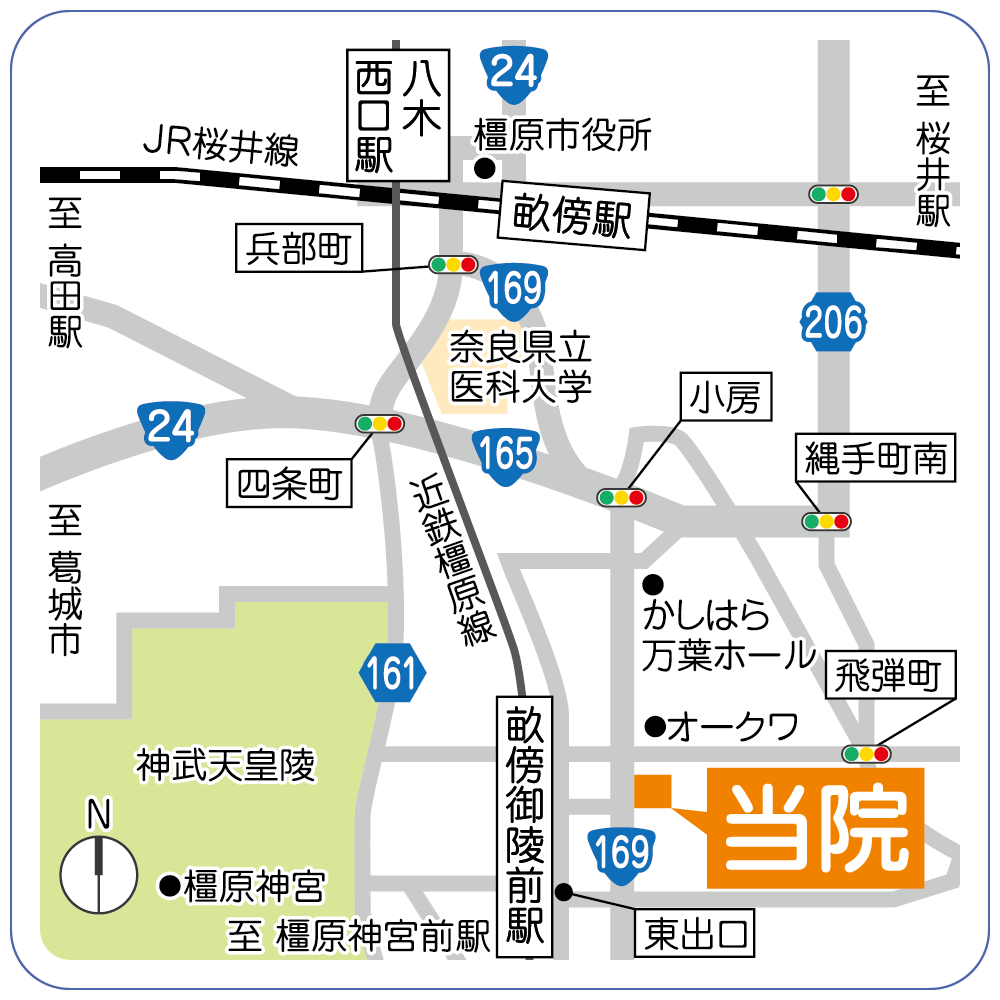眼瞼下垂は、その名の通り上眼瞼(上まぶた)が下がり、目の幅が狭くなった状態です。
上方が見えにくくなります。おでこの力を使ってまゆ毛をあげることで、なんとかまぶたを上げて見ようとするようになると、疲れを感じることもあります。
見た目だけで判断しているとお考えの方が多いですが、そうではありません。きちんとした医学的な評価方法があります。
また、見えにくさの原因となることが医学的な根拠に基づいて分かっていて、手術で良くする必要があると認められていることから、保険での手術が可能となっています。単なる見た目の変化だけの問題ではありません。
- 検査の方法
1)まず、いつからまぶたが下がっているか、何かきっかけはなかったか、時間帯によって症状が変わるか、眼科以外の病気を確認します。
2)次に眼瞼下垂の程度の評価を行います。
まぶたが下がっていることを調べるためには、上まぶたと瞳孔中心(黒目の中心)までの距離を測定したMarginal reflex distance-1 (MRD-1)があります。
MRD-1が2.5mm以下では視界が悪くなることで見え方への影響があるとされ、眼瞼下垂と診断されます。
3)続いて挙筋機能(まぶたを上げる筋肉と神経の働き)の評価します。方法は、下を見た時とから上を見た時の、まぶたの移動距離を測定します。挙筋機能が4mm以下は挙筋機能が弱い、4mmから10mmで中程度、10mm以上で十分にあるとされます。
これらは、実際の治療として手術を行う際の手術方法決定に重要な情報となります。
2.分類
病態としては、大きく先天性と後天性に分類され、さらに後天性の場合、筋性、腱膜性、神経性、機械性、外傷性に分類されます。
・先天性
単純先天下垂、瞼裂狭小症候群、Marcus Gunn症候群
・後天性
1)筋性・腱膜性
退行性(加齢性)眼瞼下垂、コンタクトレンズ眼瞼下垂、内眼手術後眼瞼下垂、外眼筋ミオパチー
2)神経性
動眼神経麻痺、Horner症候群、重症筋無力症
3) 機械性・外傷性
腫瘍による圧迫や、炎症による組織腫大からの圧迫、あるいは挙筋機能の低下などで眼瞼下垂となることがあります。
これらについてさらに詳しく知りたい方は、以前に執筆しております下記をご参考いただけますと幸いです。
金原出版
主訴と所見からみた眼科common disease
II 所見からみた診断の進め方
https://www.kanehara-shuppan.co.jp/magazines/detail.html?code=024532018095
まとめ
年齢が原因であることが多いですが、その中には脳動脈瘤による動眼神経麻痺や、眼科以外での適切な検査が必要な眼瞼下垂も存在します。
そのため、見た目だけの判断ではなく、適切な診断を行うことが重要です。
また手術となった場合は、その手術方法の選択のために正しい評価を行うことが重要です。